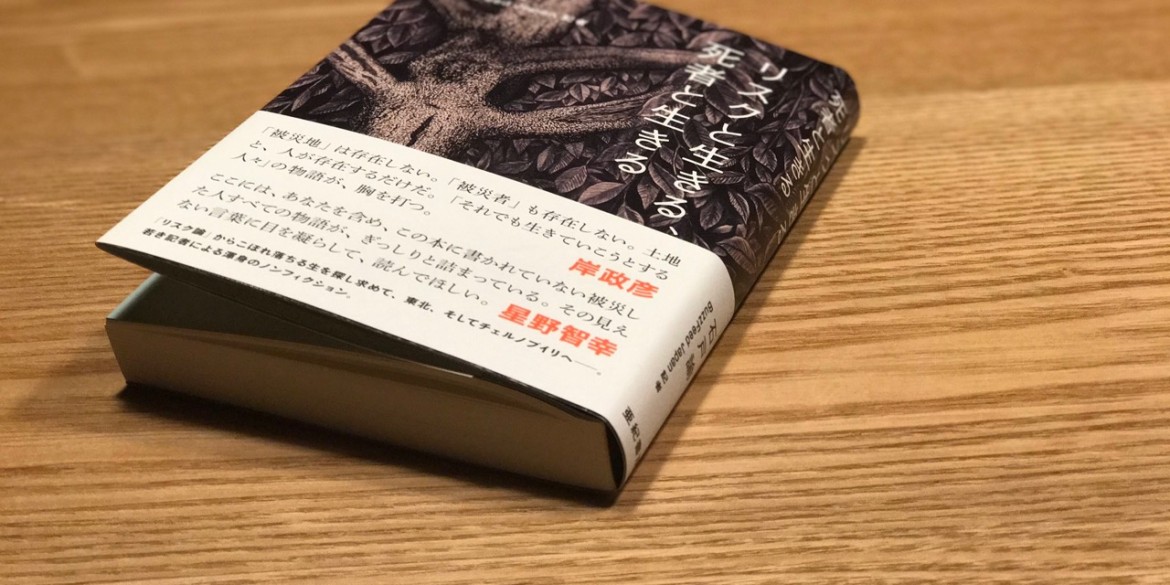分かりやすさを求める社会に抗いながら
9月29日(金)、『リスクと生きる、死者と生きる』の著者で、バズフィードで記者をしている石戸諭くんとのトークイベントがゲンロンカフェであった。とてもいい時間だった。石戸くんとは、これまで何度もやり取りがあったものの、こうして「ちゃんと」話をするのは初めてなので、とても楽しみにしていたし、3時間近くじっくりと対話できて、改めて確認できたことも多かった。
この日のテーマは「数字で語られないことで震災を語る」というもの。これは決して数字で語ることを否定しているわけではない。数字で語られることと、数字では語られないこと、その両方を見なければ、震災と原発事故で私たちは何を失ったのか、あの事故が社会にもたらしたものはなんだったのか、本当にはよくわからないままになってしまうのではないか、ということだ。
この問題意識は、「数字で語られること」がある程度出揃ってきたからこそ出てきたとも言える。健康被害が極めて最小限に食い止められたこと。流通する食品による内部被曝はもはや心配ないレベルになっていること。全量全袋検査然り、うみラボのデータ然り。科学者や物理学者たちの尽力で明らかになったものは計り知れない。
しかし、数字やデータ「だけ」では、当然個々人の喪失を語ることはできない。数字には明らかにすることのできない膨大な個々人の喪失こそ、震災と原発事故の被害を後世に伝えるために欠かすことのできない、とても重要な要素だからだ。わかりやすさを求めるメディアや、SNSがもたらす党派性や、弱者憑依された「当事者語り」によって見えなくなっていた個々人のナラティブ(本人が語る本人の言葉)を、もっと捜し求めていかなければいけない。石戸くんは本書でそんなことを訴えているように思う。
リスクという言葉に、その問題意識が凝縮されている。科学的なデータを、私たちは自分なりに読み解き、何かしらの決断をしてきた。その決断には、様々な濃淡やグラデーションがある。個々人の決断を「福島の被災者の決断」と一口に語ることはできない。正しいデータは1つしかないかもしれないけれど、各々が採った決断は無数に存在する。その決断、ひとつひとつの中に、私たちが見落としてきた原発事故のリアルが存在している。
本書のタイトルにもなっている「死者と生きる」ということ。これは喪失と向き合うということである。奇しくも、ぼくが8月に参加した「みちのくアート巡礼キャンプ」での体験にも重なってくる。死者の物語は、生者がいかに自分を恢復させながら喪失と向き合い、その喪失を後世に伝えていくか、その試行錯誤の表れでもある。後世に伝えるべき何かを死者や幽霊が語るのは、「彼らはもう死なないから」に他ならない。
東北には、そもそも日常のなかに幽霊が存在していた。震災によって、幽霊の存在意義はさらに大きくなっているようにも思う。それは、今回の震災がもたらした喪失が、あまりにも巨大だったからかもしれない。東北とは、それだけ死者を必要としてきた、言い換えれば「常に喪失と向き合わされてきた土地」だった。だからこそ、人々は「人間の想像力」を武器に、何かに抗いながら、後世に残る数多くの物語を残してきた。
分かりやすさに埋没することなく、複雑性を理解し、個々の決断を受け止めるための「リスク論」。そして、後世に言葉を届けようという「死者の存在」。その二つの視点は、そのまま「既存メディア」への批判的応答にもなる。大きな主語で語り、弱者憑依して党派性を持ち込み、安直に結論を求める言説に終始するメディア。石戸くん本人がそこに属してきたからこそ、言葉は柔らかかったけれども、批判的態度は非常に鋭いものがあるように感じた。
原発事故の複雑性を「リスク」、震災の膨大な喪失と向き合うことを「死者」というテーマに託しながら、石戸くんは、今一度現代社会に光を当てる。私たちは、このリスクだらけの社会をいかに生き、いかに他者の選択を受け入れ、そこで発生する喪失をいかに後世に伝えていくのか。そのために必要なのは、まさに数字やデータ、ファクトでは語られないこと、なのではないだろうか。
石戸くんは、取材を通じて個々人のナラティブに触れ、「数字で語られないこと」の重要さを再確認していく。その気づきは、連続性を持って本書の中に書き記されている。そんな石戸くんのナラティブもまた、本書に深みを与えてくれると同時に、震災と読者を結びつける大事な媒介になっている。
社会はますます「分かりやすく」なっている。そこから背を向け、いかにその「分かりにくさ」を粘り強く伝えていくのか。本書に書かれていることは、“純粋記者” 石戸諭の決意そのものでもあるように感じる。そしてその自問は、「伝える」ことを生業にするぼくたちにも深く突き刺さってくるはずだ。この本は、分かりやすさに生きる僕たちが、折に触れ何度も読み返す1冊になっていくのかもしれない。